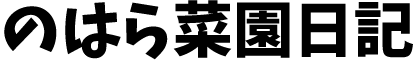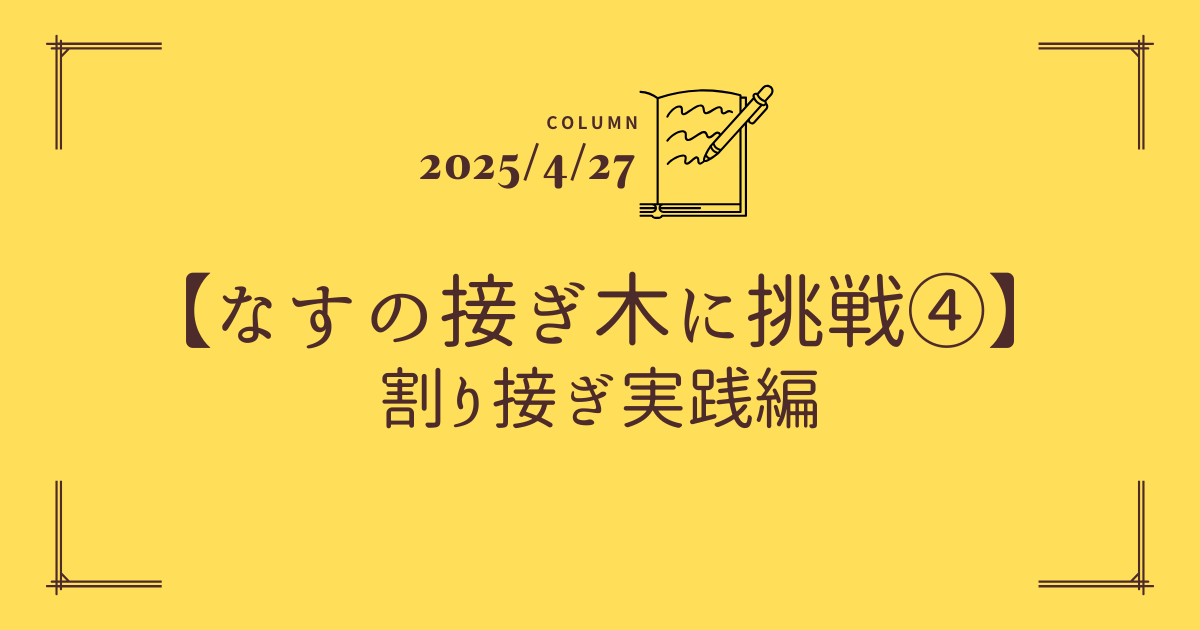皆さんこんにちは。
のはら菜園のかーくんです。
今年は接ぎ木苗の自作に取り組んでいます。
これまでの接ぎ木に挑戦①②③の記事で接ぎ木をするための準備段階を書いてきましたが、今回はついに接ぎ木作業を行いました!
その内容を紹介したいと思います。
なすの割り接ぎ
まずは台木のトナシムはこんな感じになりました。
高さが20cm強、本葉の数が7~8枚なのでやや育ち過ぎかとは思いますが、初めての接ぎ木という事で大きめに育てて準備しました。

まずは、この台木の横の葉を落とした後に、頂部の成長点を落とします。この時、接ぎ木できるようにある程度太さのあるところで切りますが、短すぎると失敗したときにやり直しが出来なくなるので、できるだけ茎を長めに残すのがオススメです。


次に、穂木のとげなし千両の上半分ぐらいを切り取り、先端をクサビ状に削ります。切断面がキレイな方が活着が速いとのことなので、スパッといってしまいましょう!(カミソリ刃でケガをしないように特に注意が必要!)
また、穂木の葉の枚数は3枚ぐらいがいいようです。葉が多いと、接ぎ木後の水分蒸発量が多くなり萎れが強くなるみたいです。


そして、台木のトナシムの中心に清潔なカミソリ刃を使って1~1.5cmほど切り込みを入れて、そこにクサビ状に削った穂木を刺しこみ、接ぎ木クリップを使って穂木と台木を密着させます。
穂木のクサビ形状が太かったり、台木の切り込みが浅すぎる場合は、接ぎ木クリップを使っても、台木と穂木が外れてしまうので調整してみてください。



接ぎ木作業後の養生方法
こんなにスパッと切ってしまった台木と穂木が本当に枯れないのか?と心配になりますが接ぎ木後の養生管理をしっかりすることで枯れずにくっついてくれます。
具体的には私の場合は以下のような条件で養生しました。
養生環境:簡易ハウス内にトンネル(ノーポリ&遮光率50%寒冷紗を2重)
養生温度:加温設備は無しで、太陽光&換気での温度コントロール
養生湿度:80~90%程度(朝にトンネル内に水滴が付着するぐらい)を目標にして、スプレーボトルで噴霧して加湿。苗が萎れたら適宜水を噴霧して加湿。
接ぎ木後の養生方法を調べると一般的に書かれている事なんですが、接ぎ木直後~3日間は完全に密閉して、寒冷紗2重掛けで養生していました。
4日目からは朝の弱い光に当て始める!と養生方法を調べると書かれているんですが、私の苗の場合はすぐに萎れが発生したので、再遮光して水を噴霧して追加で2日間ほど密閉&遮光状態で養生を継続しました。
7日目頃から日差しのまだ弱い朝に寒冷紗を半分ほど上げてトンネル内に光を入れつつ、ノーポリの裾を少し上げて風を少し入れたりしながら、苗の萎れ具合を注意深く観察しつつ、少しずつ外部環境に慣らしていきます。
日差しの強くなる日中は遮光に戻し、水を噴霧するという感じで管理していました。
正解だったのかはわかりませんが、私はまだこの時点では、じょうろなどでの水やりはせずに、水噴霧のみです。
この時点では、まだ台木と穂木が接着しているか自信がなかったで、極力負荷をかけないように管理していました。
この記事を書いている、接ぎ木後2週間目では日中でも萎れることが無くなってきたので、接ぎ木クリップを外して、じょうろでの水やりを開始しています。
また、遮光は外してしまって、トンネルも半開状態で簡易ハウス内で保温しながら育苗を継続しています。
ちなみに、現時点での成功率は98.9%(接ぎ木数191株、現時点残り数189株)となっています。
1株は接ぎ木時のクサビ形状がいびつだったようで、養生中に外れてしまいました。もう1株はうまく密着していない状態だったようで、活着しませんでした。
私としては当初成功率50~60%あればいいなと思って始めた接ぎ木苗作りだったので、今のところ大成功です!
まとめ
今回は、なすの割り接ぎ実践編を紹介してきました。
始めて接ぎ木苗作りに挑戦した感想としては、しっかりと勉強して、しっかり管理してあげると初心者でもある程度は出来るんだなという思いと、接ぎ木技術の奥深さに先人たちの研鑽に感謝の気持ちでした。
加えて、最近ではホームセンターでも接ぎ木苗が普通に売られていますが、種から単に育てた苗と、接ぎ木苗では値段が倍以上違うのにも納得です!
とても手間暇のかかった作品である事を身をもって実感しました。
苗屋さんありがとう~~~✨
定植までもう少し時間があるので、あと1~2回は苗の状態をブログで紹介できればと思います。
最期まで読んでくださりありがとうございました。
のはら菜園
かーくん