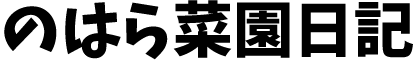みなさんこんにちは!
のはら菜園のかーくんです。
5月のゴールデンウィークが過ぎると日中の気温が25℃前後となってきて、ようやく夏野菜の植え付け適期となります。
今回は夏野菜として人気の”なす”栽培について紹介していきたいと思います。
なすは一株植えておくだけで沢山の実を収穫出来るので、家庭菜園でも人気のお野菜ですが、途中で病気になったり、害虫によってキレイな実が出来なくなったりと、長く楽しむには少しコツが必要だったりもします。
今回は、なす栽培の概略とコンパニオンプランツを使った病気予防や害虫予防についてご紹介します。
なす栽培の基本情報
まず、なすの苗を手に入れる事からスタートしますが、4月下旬~5月中旬ごろになれば、ホームセンターの園芸コーナーなどで苗が沢山売られていると思います。
おおよそ1株150円前後ぐらいのものと、1株300円~ぐらいする苗が売られたりしているのではないでしょうか?
安い方は種をまいてそのまま育てた苗(実生苗)で、高い苗は病気に強くした接ぎ木苗であることが多いと思います。
両方とも、美味しいなすを収穫できることに違いはありませんが、接ぎ木苗の方が最初の成長が早かったり、病気に強かったりするので、初心者の方にはオススメです。
また最近では、なすの種類が非常に豊富で、小さいもの、大きいもの、白いものなど様々ですが、育てやすいオススメ品種は、「とげなし千両」、「筑陽」という2品種がオススメです。
なすは本来トゲのある植物なんですがこの2種はトゲが無く、栽培しやすくて、美味しいなすが採れます!
なすは5月上旬~6月上旬ごろに植え付けて、植え付け約1か月後ぐらいから、なすを順次収穫することができます。
途中で追肥を行うと、1シーズン1株からおおよそ30~50本のなすを収穫することができます。
また、秋なすという言葉もあるように、収穫時期は6月頃~11月頃まで続き、上手に栽培管理すればとても長い期間収穫を楽しむことができます!
なすの病害虫
なすは長期間収穫できる野菜だと言いましたが、その長期間栽培ゆえに、栽培中には、梅雨、猛暑、台風など様々な厳しい気象条件にさらされることになります。
そういった時には、なすの免疫力が落ちてしまい、土壌中の病原菌や、カビなどによって病気になってしまうことがあります。
致命的なダメージを与える代表例として”青枯れ病”、"半身萎凋病"、”半枯れ病”などがあります。
植物の病気の怖いところは、治療するのが困難で、基本的な対処方法は、発症した株を撤去してほかの株に感染させない事しかありません。
家庭菜園で1~2株しか植え付けていない場合、せっかく大事に育てていたのに収穫が出来なくなってしまうので大きな損失になります。
また、なすには様々な虫が寄ってきます。
代表的なのは、”アブラム”、”アザミウマ”、”ハダニ”などになります。
これらは非常に小さな虫で、よく観察しないと見落としてしまう虫たちですが、気が付いた時には大繁殖していて手が付けられなくなる、なんてことはざらにあります。
これらの虫の怖いところは、アブラムシは病気を伝染する可能性があること、アザミウマは実の出来を悪くしてしまう事、ハダニはなすの成長を阻害することにあります。
このように、なす栽培は気象や虫など様々な条件と上手に付き合いながら長期間乗り越えていくものになります。
なす栽培におけるコンパニオンプランツの活用方法
なす栽培に色々なハードルが待ち構えていることを知ってもらいましたが、それらのハードルを越える方法としてプロ農家は、土壌改良を行ったり、苗の接ぎ木を工夫したり、徹底的な栽培管理をしたり、お薬を使ったりしています。
家庭菜園においては、プロ農家と同じレベルの管理をすることはなかなか難しいですが、比較的簡単に取り入れられる方法としてコンパニオンプランツがあります。
コンパニオンプランツについては、過去にまとめていますので、参照していただければと思います⇒コンパニオンプランツ紹介記事
こちらでは簡単にコンパニオンプランツを説明しますと、複数種類の植物を近い距離に植える(混植)ことで、お互いに良い影響を与え合う組み合わせを言います。
コンパニオンプランツを活用すると、病気が減ったり、害虫が寄って来にくくなったりするので、なす栽培に待ち構えているハードルを越えやすくしてくれます!
なすの病気を減らすコンパニオンプランツ なす×ネギ(ヒガンバナ科)
まずは病気を減らすコンパニオンプランツの組み合わせです。
なすに致命的なダメージを与える病気としては先ほども紹介しましたが、青枯れ病、半身萎凋病、半枯れ病などがあります。
これらの病気の特徴としては、土壌中に潜んでいる菌類が、なすに侵入して発症します。
対策としては接ぎ木苗を使用することが一般的ですが、接ぎ木苗も万能ではなく、苦手な病気があったり、栽培途中の管理次第では発症する事もあります。
コンパニオンプランツも完璧な対策では無いですが、病気低減効果が十分に期待できる比較的お手軽な方法です。
具体的な方法としては、なすと、ネギやニラのようなヒガンバナ科野菜を混植します。
また植え付ける際に大事なポイントがあるんですが、なすの根とネギ・ニラの根が接触するように、寄り添うように植えることがとても大事です。
なぜかというと、この組み合わせの効果が発揮されるのは、ネギやニラの根に共生している菌類の力を借りる方法だからです。
ネギに住む菌類が、なすに病気をもたらす菌類の邪魔をすることで、病気感染を防いでくれます。
これを一般的に拮抗作用と呼んでいます。
また、なすとネギを近くに植えると、栄養を奪い合って成長が遅くなるのでは?と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、なす(ナス科)とネギ・ニラ(ヒガンバナ科)では好む栄養素が違うと言われていて、両方ともよく育ちます。
小さなスペースでナスとネギを収穫出来るので、家庭菜園にはオススメな方法だと思います。
なすの害虫を減らすコンパニオンプランツ なす×パセリ(セリ科)
次は害虫被害を減らすコンパニオンプランツの組み合わせです。
なすとパセリを混植することで、害虫の飛来を抑制することが出来ると言われています。
これは、パセリの放つ香りを虫が嫌がって寄ってこなくなるというものです。
植え付け方としては、なすの畝の空いたスペースに数株植えてやればOKです。
こちらは香りが重要なので、風上、風下両方に植えられている方が高い効果が期待できます。
また、パセリは強い日光が苦手な植物として知られていますので、なすの日陰で栽培することで元気に育ちます。
なすに飛来する虫が減って、パセリも元気に育つWin-Winの関係が成り立つ、これぞコンパニオンプランツです!
一点注意が必要なのですが、香りの強い野菜は一般的に害虫を遠ざける効果が知られています。
例えば、バジルのような野菜も害虫を遠ざけるコンパニオンプランツの代表例です。
しかし、香りが強ければ強いほど虫が寄ってこなくなるだろうと、過剰に植えすぎると、かえって通気性が悪くなり、病気の原因となったり、なすの成長を阻害する原因となったりするので、植え付け量はほどほどにしておいてください。
また、混植あるあるですが、コンパニオンプランツの管理をさぼってしまい、茎葉が茂りすぎて、肝心のなす収穫がやりにくくなるなんてこともあるので、注意が必要です。
まとめ
今回は、なす栽培の概要とコンパニオンプランツの活用についてを中心に書いてきました。
なす栽培は長期戦かつハードルも多いですが、一つ一つ丁寧に対応すれば、初めての栽培でも越えられないことはありません。
ぜひスペースがあれば、なす栽培にチャレンジしてみてください。
また、コンパニオンプランツの活用記事は過去にいくつか書いていますので、読んでもらえると嬉しいです。
最期までありがとうございました。
のはら菜園 かーくん